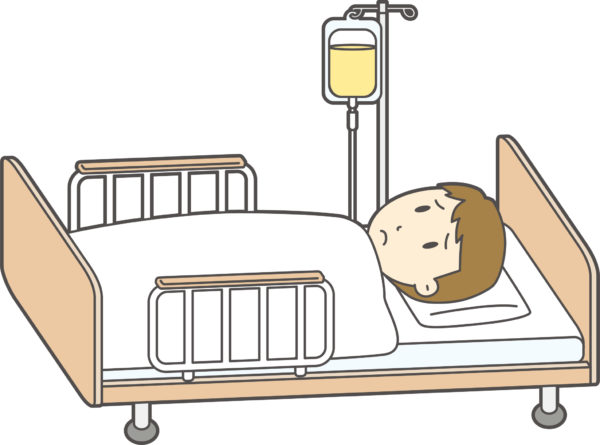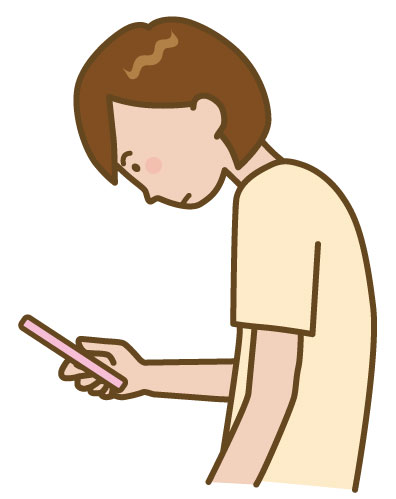顔がピクピクする…
2019.06.21
こんにちは。
随分と気温が上がってきましたね。
今日は顔の筋肉のけいれんについてお話しをします。
外来で
「顔面の筋肉がピクピクと勝手に動いて気になる」
と時折相談を受けます。
若い方は中学高校生ぐらいから、ご高齢の方まで年齢は様々です。
女性のときも、男性のときもありますが、どちらかといえば、女性が多いかもしれませんね。
やはり女性は鏡を見る機会が多く、気づくのが早いようです。
たいていは片方の目の周りに症状が出ることが多く、
あまり両方で出てくることはありません。
 少しわかづらいですが、左顔面のけいれんです
少しわかづらいですが、左顔面のけいれんです
よく見ると細かくふるえているときと、少ししっかりとパチパチしている場合とあります。
実は、みなさんの心配をよそに、多くの場合は病気と言えるものでなかったりします。
「良性眼けんけいれん」
(眼けんとは目の周囲のまぶたのあたりのことです)と呼ばれるもので、
睡眠不足や疲れで出てくることが多いものです。
ですので、少し休息を取るようにしたり、ストレスを減らすような生活をしたりすれば
知らない間に症状はなくなってしまいます。
また疲労がたまれば、出てきたりします。
一方で、なかには
「片側眼けんけいれん」
と呼ばれる、すこしやっかいな顔面のけいれんも時にみられます。
この場合は後頭部から首のつけ根にある小さな血管が
顔面にいく神経を圧迫することによって起こる症状で、
手術をしないと良くならない場合があります。
「いきなり手術?」
という方には、まず
「ボトックス」
という注射を行って症状を緩和する場合もあります。
 こんな感じで注射します。
こんな感じで注射します。
痛そうに見えますが、細い針なので
あまり痛くありません。
診察すればだいたい見分けがつきますので、
気になる方は脳神経内科や脳神経外科の医師に相談してみましょう。
頭痛のつづき
2019.06.14
こんにちは。
ジメジメの毎日ですね。
今日は頭痛のはなしのつづきをしますね。
前回までに、片頭痛と緊張型頭痛についてお話ししてきました。
今回はその他の「頭痛の原因となる病気」について述べましょう。
まずは有名な“くも膜下出血”があります。
脳のなかに起こる出血で、
一般的には
「突然に」
「何時何分のこの瞬間に起こった」
とわかる激しい頭痛が特徴です。
このくも膜下出血は、これまで述べた頭痛と異なり、
生命の危険を伴うために緊急の医療対応が必要です。
「晴天の霹靂」とも例えられるような頭痛が起きたら、
医療機関にすみやかに相談する必要があります。
なかにはごくまれに、このような急な経過をとらないくも膜下出血もあります。
“なんとなく、いつからとは言えない経過”で発症した重い頭痛で、
通常の外来を受診して脳のCTを撮影したら実はくも膜下出血だった、なんてこともありました。
そのほかにも、頭痛を訴えて受診し、脳のCTを撮影したら大きな脳腫瘍だったこともあります。
かぜをひいて、熱が出て、頭痛を伴うことはよくありますよね。
熱を伴う頭痛の中には脳髄膜炎といって、脳を包む膜の炎症ということがあります。
細菌が原因の髄膜炎はとてもやっかいで、入院の必要があります。
また同様に、
おでこの辺りの痛みでMRIを施行してみると副鼻腔炎(鼻の奥の細菌による炎症)だったこともあります。
このように頭痛を呈する原因は、色々とあるために
病歴とあわせてきちんと診断することが重要ですよね。
緊張型頭痛
2019.06.08
こんにちは。
東京も梅雨入りとなりました。
みなさまはいかがお過ごしでしょうか?
わが家のアジサイも少しずつ花がついてきています。
今回は、前回に書いた頭痛のはなしの続きをいたします。
発作のように症状の出る片頭痛とは異なり、
緊張型頭痛はなんとなくダラダラと頭痛症状があります。
いつも重い感じがして本当に嫌なものなんです。
疲れや寝不足で症状が強くなります。
首まわりの筋の重労働が原因なので、
パソコン作業の長い人、
運転手さん、
乳児をだっこすることの多いお母さん、
前掛けなど首から物をぶら下げて仕事をしている人
に多く、また
夜勤のある生活で睡眠が不規則になりやすい人も、
睡眠中に筋の疲れがうまくとれず頭痛となる方が多いです。
最近では、スマートフォンを見る時間が長く、その姿勢の問題や
光の刺激による睡眠の質が問題視されていますよね。
この頭痛では、その名のとおり首のまわりの筋肉が固くなっています。
筋の緊張をやわらげる薬で、症状の軽減をこころみます。
しかしこういった薬は同時に眠気を誘うものが多く、実際には飲みづらい薬が多いのです。
外来では運動不足・睡眠不足の解消、睡眠の質の改善などの指導をします。
それと同時に、
実は首まわりの筋力を改善させるリハビリテーションで頭痛の改善がみられることも多くあります。
日常生活の工夫で、症状の改善を期待できるので、ぜひ専門医にも相談してみましょう。